前回のブログをAIに読み込ませて、感想を聞いてみたところ以下の2点のフィードバックをもらいました。
・kolorに関する言及が少ない
・分析がやや薄く、評論としての奥行きが弱い
もっともなフィードバックだと感じたため、今回はジョナサン・アンダーソンの世界観と、彼がLOEWEの売上を引き上げた原動力について掘り下げてみたいと思います。
ジョナサン・アンダーソンは、いまやLOEWEというハイブランドのイメージを大きく刷新した中心人物として、またJW Andersonでの先鋭的なデザインでも注目されています。
本稿では、彼のデザインに通底する「ポスト・ジェンダー」という思想を出発点に、なぜアンダーソンの服が新しいのか、そしてなぜ“売れる”のかを考えてみたいと思います。
なお、本稿はAIとの「壁打ち」をもとに執筆しています。
■根底にある「ポスト・ジェンダー」
私は、毎シーズンのコレクションにおける存在感が非常に高かったように思います。必ず、インスピレーションを受けたソースが存在し、その世界観を洋服の形に落とし込み、表現していました。
アンダーソンの発言として、
「服は性別のためのものではなく、アイディアの媒体である」
という一節があります。
この言葉には、従来の「ユニセックス」や「中性的ファッション」とは一線を画す哲学が感じられます。
従来のユニセックスは、「男性性/女性性を曖昧にする」ことで中間地帯をつくるものでした。対してアンダーソンは、そもそも性差というカテゴリそのものを前提としない美学を服に落とし込んでいます。
これは「性差を乗り越える」のではなく、「性差が最初から重要ではない」という立場。つまり、「ポスト・ジェンダー」という視点です。
■ジェンダーを“テーマ”ではなく“素材”にする
この哲学は、JW AndersonやLOEWEのコレクションにも色濃く表れています。
たとえば:
- メンズの服にラッフルやスカート、ドレープといった意匠を組み込む
- レディースの服に硬質な素材、直線的な構造を与える
- 性別に意味を持たせない装飾やカッティングを多用する

2013年コレクションより引用
ここで注目すべきは、これらが“ジェンダーを語るため”に施されているのではなく、デザインそのものに組み込まれている点です。
つまり、「デザインがジェンダーを超えている」ことが主題なのではなく、“ジェンダーを気にせずとも成り立つデザイン”を実現していることが重要なのです。
■比較から見えるアンダーソンの特質
このスタンスは、たとえばThom Browneのような「ジェンダー規範を戯画化し、解体する」タイプとも異なります。また、Rick Owensのような身体性・性差を大胆に強調・操作するスタイルとも距離があります。
アンダーソンのアプローチは、構造的なデザインの中にジェンダーという軸を“消し込んでしまうこと。その静かな前衛性が、彼の服の大きな特徴です。
■なぜそれが「売れる」のか?
ここで一つの疑問が生まれます。
——このような思想的に高度な服が、なぜハイブランドのビジネスとして成立しているのか?
答えは、「思想を直接伝えるのではなく、感性として表現している」からではないでしょうか。
アンダーソンの服は、思想を解説しなくても美しい。そこに「着る人の性別を問わない構造」がさりげなく織り込まれている。この思想と構造の“非対称さ”が、LOEWEというブランドを支持する多様な層に自然に受け入れられているように見えます。
■終わりに
ジョナサン・アンダーソンの服は、「男性らしさ/女性らしさ」という枠組みから自由になった美しさを提示しています。それはポリティカルな主張ではなく、美的な選択肢として機能している点で、現代ファッションの中でも異彩を放っています。
この“語らない哲学”が、LOEWEのブランド価値を支えている——。
次回は、この哲学がどのように売り上げにつながっていったのか、マーケティングと商品構成の観点からさらに掘り下げてみたいと思います。
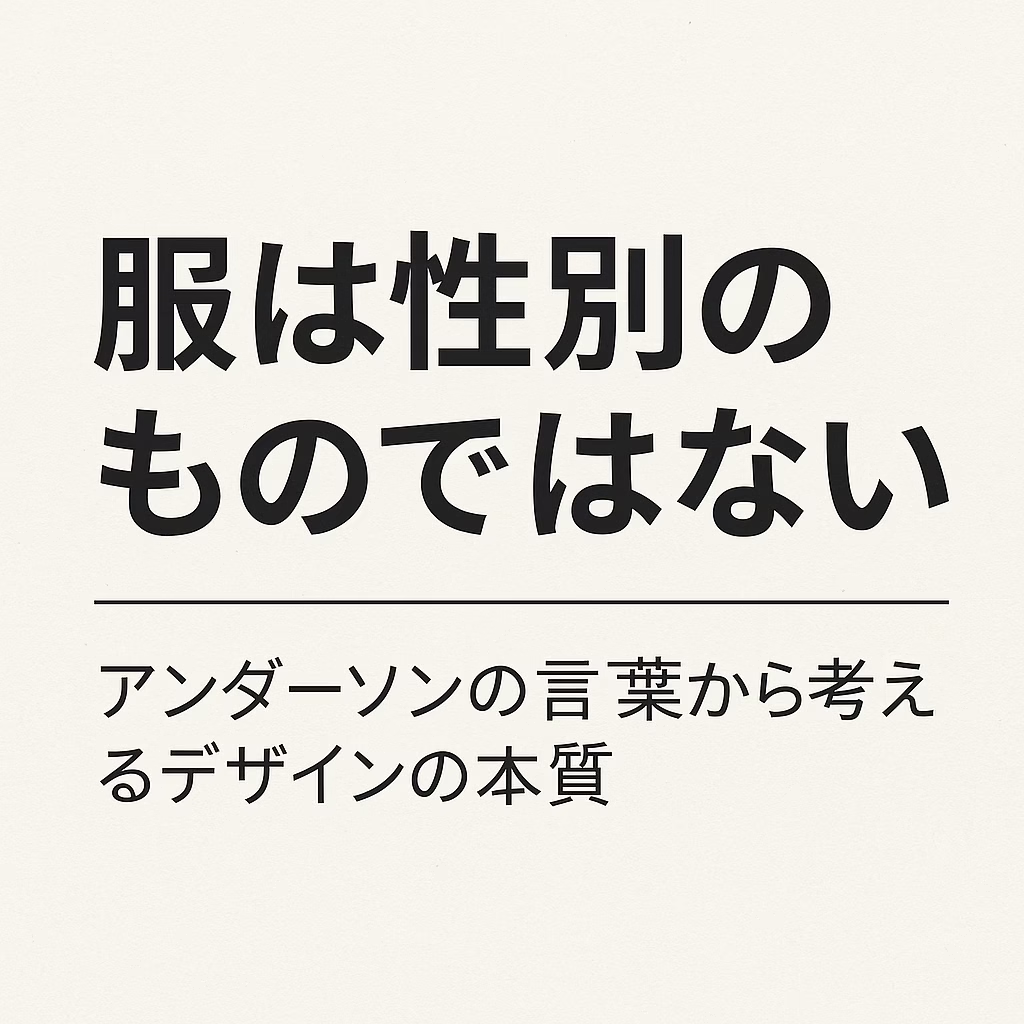
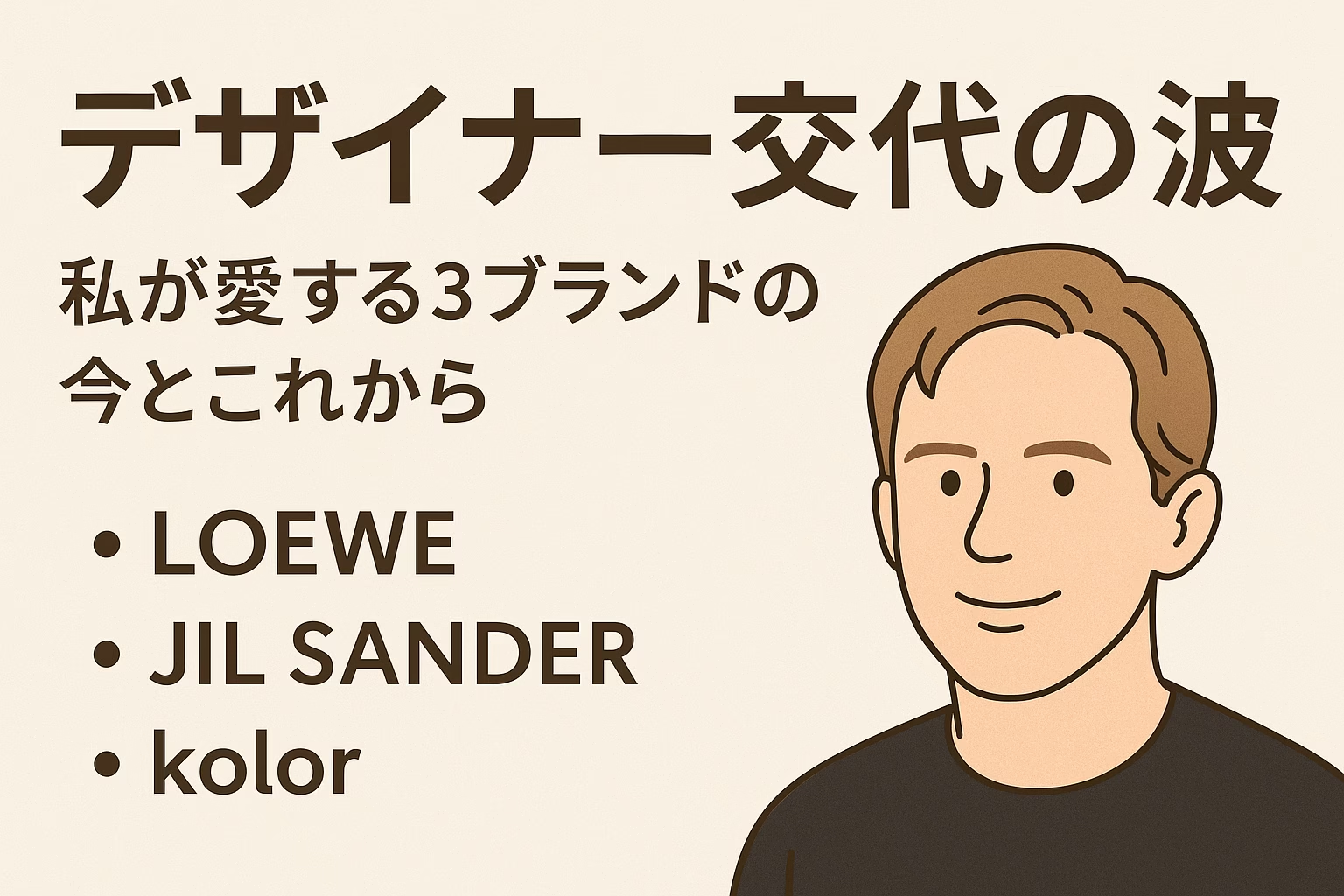
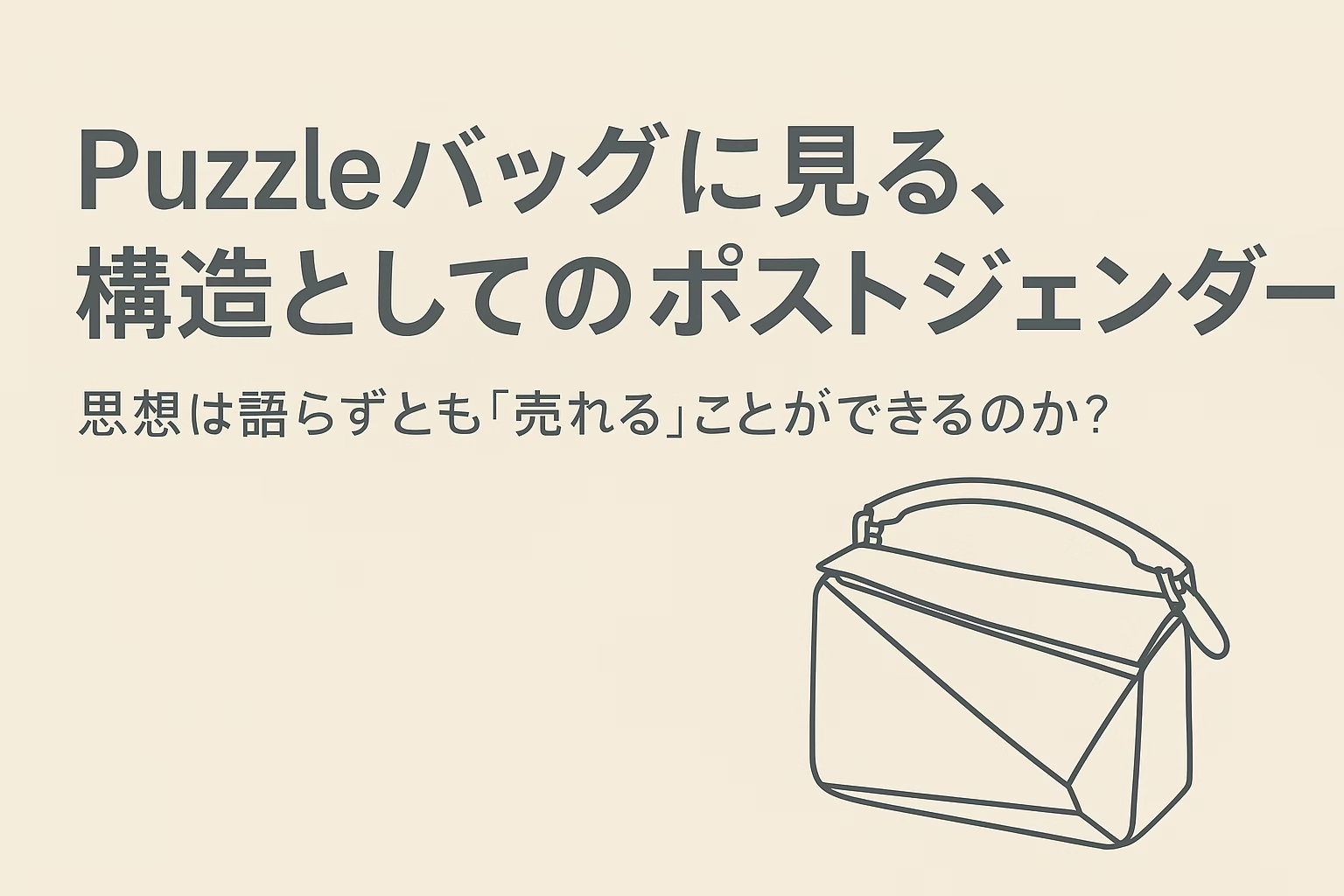
コメント