前回のブログにて、kolorに惹かれた個人的な経緯について書いてみました。
今回はもう一歩踏み込んで、kolorのデザインに宿る美意識や、そのルーツについて考察してみたいと思います。そして後半では、同じく“編集的なアプローチ”を得意とするブランド、sacaiとの違いについても触れてみます。
■kolorに息づく“呉服屋の感性”と“現場仕込みの編集力”
kolorを率いるのは、デザイナーの阿部潤一さん。ご実家は呉服屋を営んでおり、子ども時代は色とりどりの反物や半襟のサンプル帳に囲まれて育ったといいます。布を染めたり、色の組み合わせを試したりする中で、繊細な色彩感覚を自然と身につけた──そんな幼少期の原体験が、現在のデザインにも深く反映されていると思います。
阿部さんは文化服装学院アパレルデザイン科を卒業後、コム デ ギャルソンに入社。やがてジュンヤ ワタナベ氏のチームで経験を積み、パリコレクションの発表にも関わります。その制作過程では、パリの古着店で買い付けた大量の古着を日本に送り、分解し、再構築するという“実践的な訓練”が日常だったといいます。
※Vogue Japanのインタビューより
私はこの体験こそが、kolorの独特なテーラリングの基盤になっているのではないかと感じています。
■kolorの「ミニマル・アンバランス」
kolorの服には、一見プレーンに見えて、よく見ると微細な“ズレ”や“違和感”が巧みに仕掛けられています。たとえば、シンプルなカットソーに施された極細のパイピング、左右非対称に配置されたポケット──それらは機能ではなく、視覚や感覚を刺激するための意図的なノイズです。
こうした繊細な変奏は、おそらく幼い頃に半襟の端切れを組み合わせて遊んだ経験、「ほんの少しの差異を楽しむ目」をルーツにしているのかもしれません。また、素材の選定も印象的です。オーガニックコットンと化繊混紡のような、異なる質感同士のコントラストを活かすレイヤードは、まさに“質感の再編集”。ミクロな視点で服を再定義するkolorの姿勢が、ここに凝縮されています。
仲良くさせていただいているショップの店員さんから聞いた話では、阿部さんはいつも無数の生地に囲まれながら、細部にまでこだわって生地選びをしているそうです。その姿勢が、手に取ったときの“驚き”や“発見”として服に表れているのだと、深く納得させられるエピソードでした。
■sacaiの「ハイブリッド・アーキテクチャ」
阿部潤一さんの妻・阿部千登勢さんが手がけるsacaiも、解体と組み換えの美学を軸としたブランドとして知られています。ブランド名に“c”と“k”を入れ替えたという逸話も象徴的ですが、そのデザインの方向性はkolorとは大きく異なります。
sacaiの服は、素材や構造そのものを大胆に組み替えることで、複数のスタイルや機能を一つの服に共存させるのが特徴です。ニット×ナイロン、ウール×シルクなど、相反する質感を組み合わせたり、前後で別の服を縫い合わせたような構造に仕上げたり──そのアプローチは、“構造の再構成”とでも呼びたくなるものです。袖や背面、裾など、あらゆるパーツが再定義されることで、sacaiの服はまるで「動くインスタレーション」のように、着る人の動きに応じて多層的な表情を見せてくれます。
■解体と再構築がもたらす日常のアップデート
kolorとsacai─どちらも「服を一度壊して、もう一度組み立て直す」という点では共通していますが、その解釈とアウトプットはまったく異なります。kolorは、日常着のフォーマットの中に微細なズレを仕込み、着る人の感性に静かに問いを投げかけます。一方のsacaiは、服という“構造物”そのものを再設計し、ファッションのルールを更新していきます。
言い換えれば、kolorは「日常の輪郭をにじませる」、sacaiは「日常の前提を塗り替える」。そんなふたつのブランドが、それぞれの手法で私たちの生活に新しい視点や体験を差し込んでくれるのは、とても刺激的なことだと思います。

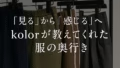
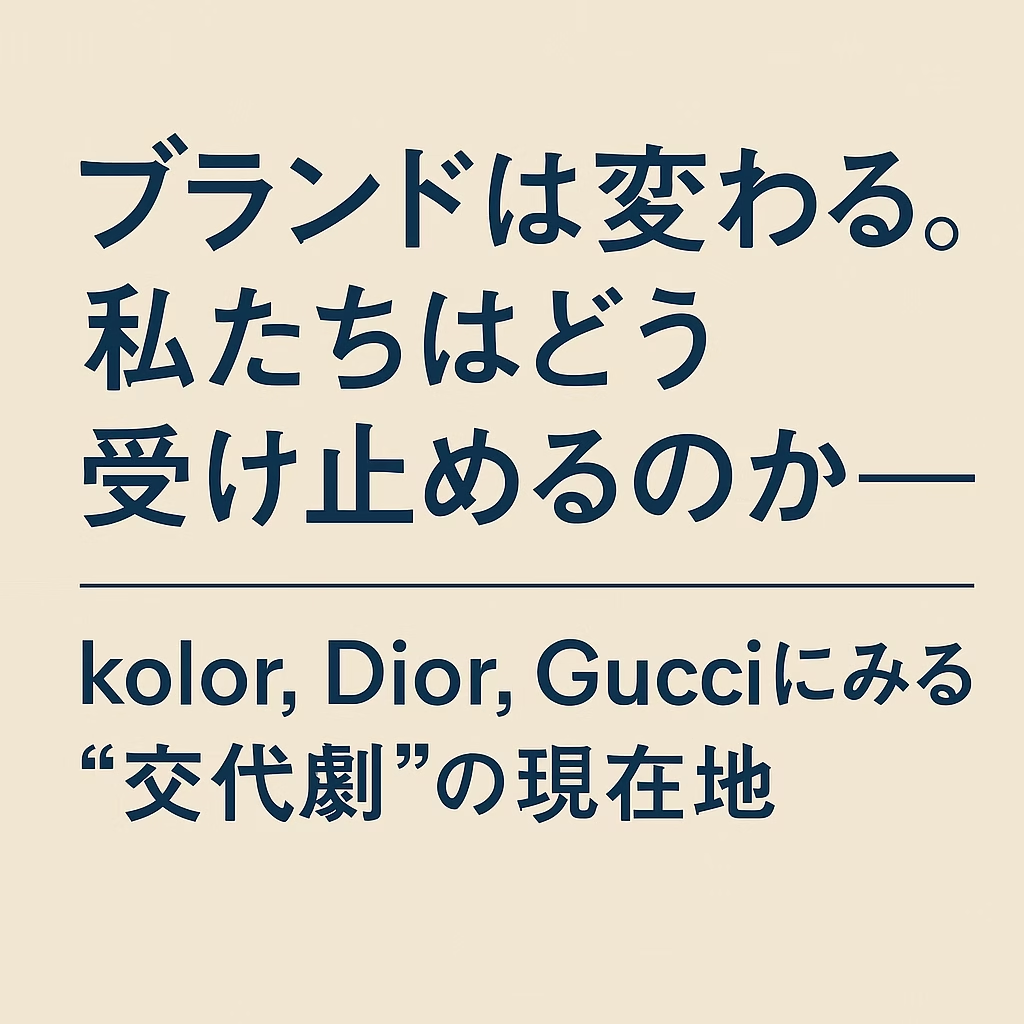
コメント